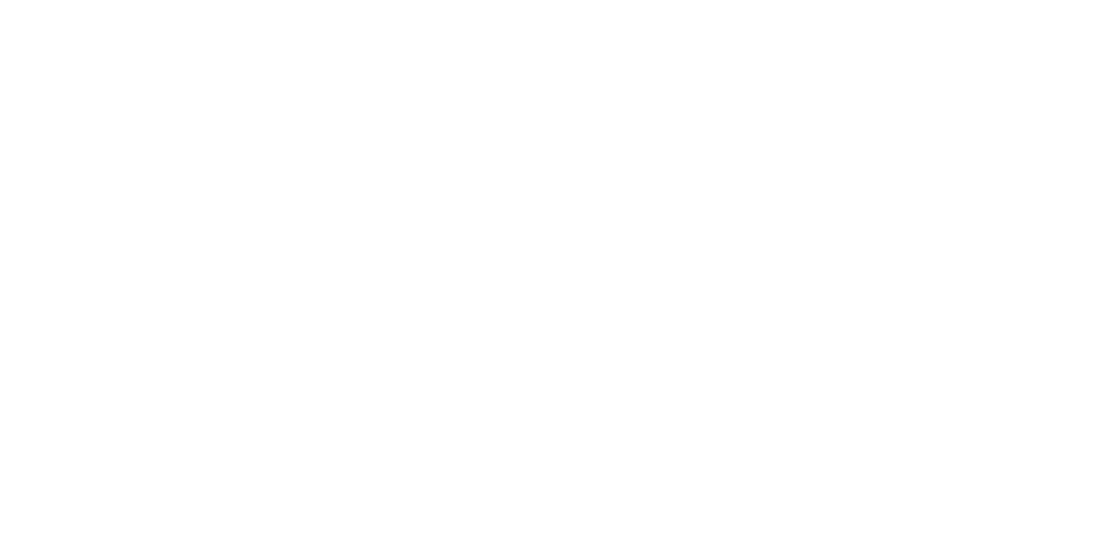
蔦屋重三郎は、時代を代表する出版業者として、葛飾北斎や喜多川歌麿、滝沢馬琴、大田南畝といった数々の文化人や作家たちを世に送り出し、町人文化の発展に寄与しました。2025年1月から放送の大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」では主人公として取り上げられます(主演は横浜流星さん)。ここでは、そんな蔦屋重三郎の人生に深い影響を及ぼした場所や、蔦屋重三郎を取り巻く人物達の縁の地を紹介していきます。

江戸幕府の老中として積極的な経済政策を推進し、商業の発展を促した田沼意次。その風潮に背中を押されるようにして、蔦屋重三郎は数々のヒット作を世に生み出しました。そんな、間接的に蔦屋重三郎の後押しをした田沼意次の屋敷は、現在の「神田橋」あたりにありました。この田沼意次の屋敷には、便宜を図ってもらおうと、贈り物を持った商人達が毎日押し寄せたそう。大河ドラマ「べらぼう」ではこの田沼意次を俳優の渡辺謙さんが演じます。

現在「神田橋」が架けられている場所には、1629(寛永6)年、真岡藩の藩主であった稲葉雅勝(いなば まさかつ)によって建てられた「神田橋門」がありました。江戸五口の一つに数えられた「神田橋門」は、将軍が上野の寛永寺や日光東照宮に参拝するときに通る道として使われていました。
松平定信の幼名は田安賢丸(まさまる)として知られ、大河ドラマ「べらぼう」では寺田心さんが演じます。松平定信は、九段下駅より徒歩5分の「北の丸公園」内にある「田安門」西側の田安家で1759(宝暦9)年に誕生。「田安門」は、松平定信の先祖にあたる松平忠昌らによって1629(寛永6)年に修繕されました。現在の田安門はもともとその土地にあった「田安大明神」という神社(現在の築土神社)が名前の由来と言われています。
これまで何度か修繕が行われたものの、江戸城で現存する最古の城門として残されている「田安門」。江戸時代の歴史と建築技術を今に伝える重要な貴重な遺構として、国指定重要文化財にも指定されています。

この松平定信が行った寛政の改革では、戯作や浮世絵が風紀を乱すとされ、表現への規制が厳しくなったと言われています。蔦屋重三郎が刊行した出版物も規制の対象となりました。
江戸時代、町の治安や秩序を守るため、警察や裁判所のような役割を担っていた「南町奉行所」と「北町奉行所」。松平定信が老中に就任したのち「北町奉行所」から蔦屋重三郎は、財産の半分を没収される身上半減(しんしょうはんげん)の罰が下されました。

「北町奉行所跡」は現在のJR東京駅日本橋口付近に置かれていました。なお”遠山の金さん”の名で知られる遠山左衛門尉景元(とおやまさえもんのじょうかげもと)も、この「北町奉行所」で3年間ここで奉行を務めたと言われています。
徳川御三卿の一つである一橋家の二代目当主、徳川治済(とくがわ はるさだ)は田沼派を一掃した人物として知られています。「べらぼう」では生田斗真さん演じる徳川治済は、江戸城の「一ツ橋門」内側に構えられた屋敷で暮らしていました。

2017年、この屋敷の庭園の池跡や堀の遺構が発見され、建物の一部が明らかになったとされています。現在は日本橋川に架かる「一ツ橋」があり、近くに「一橋徳川家屋敷跡」の石碑も建てられています。
江戸の長編よみもの「南総里見八犬伝」などで知られる戯作者の滝沢馬琴(たきざわ ばきん)。この滝沢馬琴の初期のキャリアを支えたのが、当時本屋と出版業者である版元をしていた蔦屋重三郎です。滝沢馬琴は、蔦屋重三郎に見込まれ、手伝いとして働きながら執筆をしました。
そんな滝沢馬琴が住居を構えていたのが現在の九段下一丁目にあたる場所。1793(寛政5)年27歳で当時「飯田町中坂」と呼ばれたこの地の履物商伊勢屋に蔦屋重三郎等の勧めもあり婿入りし、58歳で神田同朋町に移るまで住んでいたと言われています。現在は、滝沢馬琴の自宅の井戸のあった場所に「滝沢馬琴の硯の井戸跡」として石碑が残されています。
作家、戯作者、発明家、蘭学者などさまざまな肩書きを持つ江戸の有名人、平賀源内。中でも、小説「浄瑠璃」の執筆や、摩擦で静電気を起こす機械「エレキテル」の復原やさまざまな発明で広く知られ、現代の文化や科学技術にも影響を与えています。蔦屋重三郎が初めて編集者として手がけた、吉原の案内書「吉原細見」(よしわらさいけん)は、平賀源内が序文を担当したことで、人々の注目を集めました。大河ドラマ「べらぼう」では、物語の主要人物として俳優の安田顕さんが演じます。

平賀源内が29歳のときに入学した「湯島聖堂」は、現在も御茶ノ水駅近くに史跡として残されています。平賀源内はこの学問所で学びながら、寄宿舎で生活していました。ここでの経験から、多くの知識を身につけ後のさまざまな分野での活躍の礎をつくったと伝えられています。
1690年徳川綱吉により現在の湯島に移され、湯島聖堂となった。開設当初は私塾として始まりましたが、後に幕府が運営する所管学問所に発展しました。聖堂には儒学の創始者である孔子が祀られています。
江戸を代表する狂歌師や随筆家として知られる大田南畝(おおた なんぽ)。特に狂歌では、唐衣橘洲や朱楽菅江とともに「狂歌三大家」と呼ばれ、高い評価を得ていました。蔦屋重三郎は、大田南畝が歴史に残した数々の作品に出版者として携わっています。大田南畝が書いた「嘘言八百万八伝」も蔦屋重三郎が版元として世に送り出しました。

御茶ノ水駅から徒歩1分の「御茶ノ水ソラシティ」が建つ土地には、かつて大田南畝が「緇林楼(しりんろう)」と名付け晩年過ごしていた住居がありました。2階建ての十畳の部屋は彼の書斎や客間として使われ、当時の 文人の交流の場として知られています。
御茶ノ水駅より徒歩5分の「神田神社」。境内には、国学者の荷田春満が江戸で初めて国学の教場を開いた場所が神田神社社家の芝崎邸であったことから、「国学発祥の地」の石碑が建てられています。国学に精通していた大田南畝も狂歌のなかで「神田明神」に触れています。

東京都千代田区を中心に神田、日本橋、秋葉原、大手町、丸の内など108の町会で構成された神田明神氏子町会。この神田明神氏子町会には、平賀源内や滝沢馬琴の住居がありました。
田沼意次の政策によって支えられ、松平定信の取り組みによって苦しめられた蔦屋重三郎。ですが蔦屋重三郎は新たな工夫と挑戦を重ねて江戸文化の発展に尽力し続けました。そんな蔦屋重三郎に影響を与えた人物の縁の地を巡ることで、大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」をより深く楽しむことができそうです。